この記事は、キッチンスケールを使った料理上達が早くなる3つの方法と、キッチンスケールの選び方をお伝えする記事です。
予想以上!キッチンスケール効果

わざわざキッチンスケールって、少し面倒くさい気がします。

思っている以上に結果がでやすいので、ぜひ、チャレンジしてみてください!
私自身、料理をするようになってから2年くらいはキッチンスケールを持っていませんでした。美味しくつくりたいという気持ちはあったのですが、そこまでしなくても、と思っていたのです。
そんな自分でしたが、あるレシピ本を購入したのがきっかけでキッチンスケールを購入し、量ることを初めてみました。すると、想像以上に味が整う。そのうえ、次回への改良点も見えてくる。今ではキッチンスケールがないと不安になってくるほどです。それもどうかと思うのですが。
この記事では、自分が感じたキッチンスケールのお話をさせていただきます。キッチンスケールが気になっている方の参考になればと思います。
ぜひ、ご覧ください。
料理上達が早くなる3つの方法
キッチンスケールを使った料理上達が早くなる方法は次の3つです。
それぞれを次で説明します。
①レシピを正確に再現する(基準の味を知る)
味の好みは人それぞれですが、まずは一般的な(基準の)味付けを知ることが大切です。そのためにキッチンスケールで正確に材料や調味料を量り、なるべくレシピどおりに再現し、一般的な「美味しい」味を再現して食べましょう。
とにかくあぜらずに丁寧に作りましょう。あせらない為には準備をしっかりするのが大切です。加熱などによる材料の色や形の変化とレシピ写真を見比べながら調理するのもポイントです。
- ゆとりを持って丁寧に
- 調理を始める前にレシピを読んで流れをイメージする
- 材料のカット、調味料の計量は調理の前に
- 材料、調味料の分量は正確に
- 手順の順番を守る
- レシピ手順写真の材料の色や形を観察する
最初は、プロの料理人が書いた基本や定番メニューのレシピがオススメです。時短を強く意識したりアレンジが強い料理のレシピよりも、いろいろな料理に応用できます。
- 写真が多いレシピ
- 調味料、素材がグラム表示(玉ねぎ中1個ではなく、玉ねぎ200g)
- プロの料理人のレシピ
- 基本、定番メニュー
- 時短メニューは避ける
②材料や調味料を量るクセをつける(分量感覚が身につく)
はじめは玉ねぎ100gがどのくらいか分からないかもしれませんが、経験を積むと目安がつかめるようになります。キッチンスケールで量る習慣をつけることで、食材や調味料の分量感覚が身につき、手際が良くなり、応用力も高まります。
- 分量感覚が身につく
- 材料を見て、味付けに必要な調味料をイメージできる
③自分の好みの味を記録する(正確な再現と次回への課題)
レシピを自分の好みの味にあれこれ調整していくのは、自炊の大きな楽しみのひとつです。食材や調味料の量を正確に記録ですると、次に作る時に簡単にを再現したり修正したりできます。
「前回よりも少し味を薄くしたいけど、前回はどれくらう醤油を入れたのか憶えていない」などという悔しい思いしなくてすみます。
- 調味料、材料等の分量
- 材料のカットの形、大きさ
- 手順
- 加熱時間
- 食べた感想(美味しかった、もっと甘い方が好み、など)
これは料理人や料理の上手な人をリスペクトした上での話です。料理が上手なひとほど、調味料等の分量は「てきとうでいいよ」なんて言いますが、それは、長年の経験と技術があってこそです。初心者のうちは「基本の量」を守り「基本の味」の再現から始めるのをオススメします。
間違いない選び方
ここでは、初心者が買うべきキッチンスケールの間違いない選び方のポイントと理由を説明します。
結論 3kgまではかれる、0.1g単位のシンプルなデジタルタイプの物
なぜ「3kgまではかれる、0.1g単位のシンプルなデジタルタイプの物」を選ぶのか?大きな理由は次の2つです。
- いろいろな料理に対応できる
少量から多量までが量れ、わずかな調味料も計測でき、料理の幅が広がります。 - ストレスなく使勝手が良いから、毎日気軽に使える
大きくて出しにくい、使い方が難しいなどのストレスが少ない物は、毎日気軽に使えます。
5つの選ぶポイントと其の理由
キッチンスケールを実際に選ぶ時にチェックする5つのポイントに分けて説明します。
- ①3kgまではかれる
- ②0.1g単位ではかれる
- ③コンパクト(デジタル式)
- ④使いやすい(必要最低限な機能)
- ⑤掃除が簡単
- フライパンや鍋ごと計量できる
- 複数人数分の料理に対応
キッチンスケールを使う事に慣れてきたら、フライパンや鍋に直接材料を入れて、フライパンや鍋ごと計量すると、ボウルなどのを使わずに済み洗い物が減ります。
1人暮らしでも、作り置き等のため4食分(4人分)つくる事も想定すると3kgまで量れると余裕があります。
1食分(1人分)の炒め物等の料理の重さは200g前後。4食分だと800g前後です。4食分の調理が可能な26cm深型タイプのフライパンの重さが1kg前後。合計で1.8kgですが、煮汁や茹でる事が必要な煮物や麺類の場合重量は増すので、3kgまで量れると、安心していろんな料理に対応できます。2kgでもたいていまにあいますが、2kgも3kgまでの商品も、そんなに金額の差はないので、買うなら3kgがオススメします。
- 塩、スパイス、イースト等、こまかい計量が必要な物に対応
主に調味料、スパイスなど数グラムを計量する時に1g単位だと誤差が0.5グラム以上になってしまう可能性があります。これは、つくる料理によっては大きな問題です。
- 邪魔にならない大きさ
流し台や食卓など、限られたスペースの中でストレスを少なく使うには、コンパクト(小さい事)なのは必須です。おすなると、アナログ式よりも小さいデジタル式がオススメです。
- ①電源ON、OFF
- ②0表示(容器の重さを差し引いて計量できる)
この二つの機能が必要最低限の機能です。スマホと連携できるものや、いろいろなモードや計算ができる商品もありますが、必要最低限の機能だけのものは設定などもいらずに使いやすいです。
- 清潔を保ちやすいシンプルなデザインとつくり
とくに変わった形を選ばなければ問題はないですが、汚れた時にサッと拭けるような商品がオススメです。
オススメ商品
ここでは、2つのオススメ商品を紹介します。タニタ製とドリテック製です。両社とも、測定機器等を製造販売する日本のメーカーです。どちらの商品も先ほど紹介した条件をクリアしています。詳細は次のリンクからご確認ください。
ちなみに私はドリテック製の商品を使っています。ディスプレイが大きくて見やすいです。
タニタ製
体組成計や体重計などの健康計測機器を製造・販売する健康総合企業です。
ドリテック製
家庭用、医療従事者向けの電気機器や計測機器を開発・製造・販売する日本のメーカーです。
まとめ
以上、この記事では、キッチンスケールを使った上達が早くなる3つの方法とキッチンスケールの選び方を紹介しました。
わたしの考えるキッチンスケールの最大の利点は「味を記録して次に活かせる」事です。次に作る時はもう少し甘くしたいな、などと思っていたのに、いざ作ろうと思うと前回の味付けを憶えておらず、またふりだしに戻っちゃう、という事ばかりでしたが、キッチンスケールを使う用になってからは、毎回前進できている実感があります。
はじめは少し面倒くさい感じるかもしれませんが、繰り返していくと、わりとすぐにあたりまえになってきて、自分の確かな情報として蓄積されていくのも嬉しいです。
みなさんの美味しく面白い自炊に、今回の記事がお役に立てたら幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
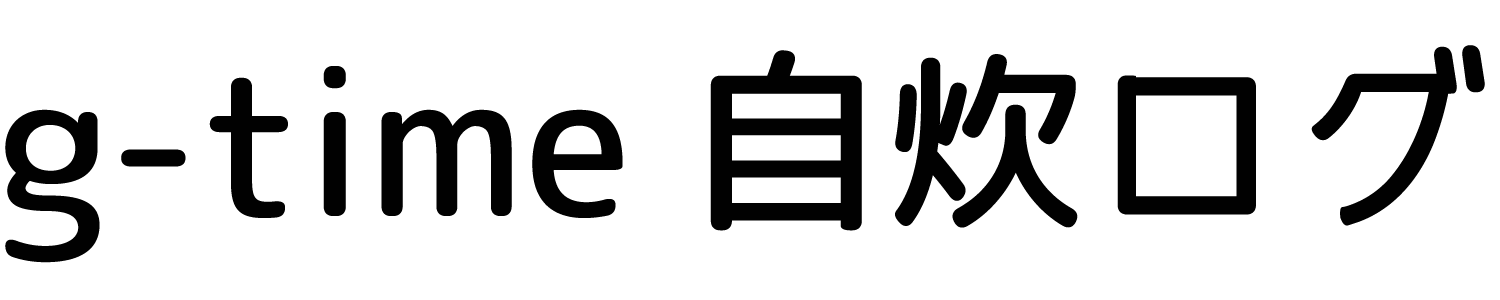


コメント